湖北てぬぐいができるまで~注染工場編~

山に降った雨や雪が
土に浸み、湧き出し
びわ湖へと注ぐ つかの間
みずみずしい湖北の暮らしを彩る
愛しい風景をモチーフにした
てぬぐいです
もくじ
その2 注染工場編 「注染」の技を知る旅へ
〇 今回の登場人物 〇


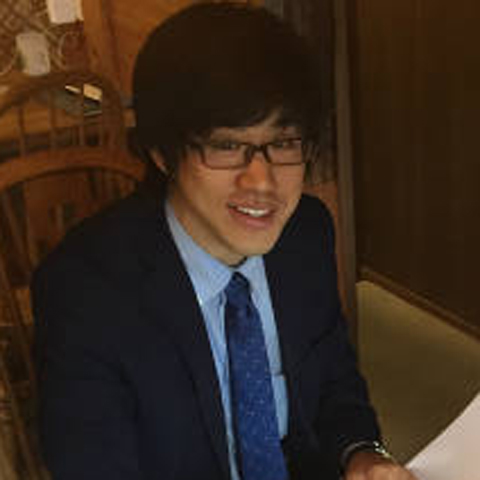
風に舞う長い長いてぬぐい まつわるヒストリー
住宅街のどんつきに突然あらわれる工場。入り口には、風に揺られてたなびく何枚もの長い生地……思わず惹きつけられる光景が広がります。 ここは、大阪府堺市にある協和染晒工場。

入口に吊るされていたのは、染色が終わって乾燥させていた晒生地。花柄、ドット、文字、さまざまなデザインが色鮮やかにゆらゆらと風のなかを泳いでいます。

「きれいやろ?この花柄のは浴衣の生地やわ。手ぬぐいはもともと浴衣の反物の余り生地を使こたんやで。だから手ぬぐいて切れっぱなしやろ」
そう教えてくれたのが、羽衣綿業の日野谷哲也さん。今回の見学の案内役にもなっていただいた方です。

協和染晒工場では、「注染」と呼ばれる技法で晒生地の 染色を行っています。ごく簡単に説明すると、染料を生地の表からも裏からも浸透させ染めあげる技法のこと。
「プリントの場合やと生地の上から色をのせるだけや。けど注染は生地の糸に染め込ませる。だから通気性がいいし、晒の生地の良さをそのまま伝えられる。何より使い込むほどに色に味わいが出てくるんや」
と、工場から出てきてくれた協和染晒工場の社長、小松隆雄さんが説明してくれます。

注染の技法が生まれたのは明治時代のこと。一帯は綿の晒加工・染色の産地として栄えた地域でしたが、現在注染を行うのは4軒のみ。さらに女性用浴衣を注染で仕立ててくれるところは、全国でも2軒だけ。 協和染晒工場はそのひとつでもあるのです。
数字では測れないもの、
身体と経験でしか得られないもの。

真っ白い晒生地の上を、なめらかに、まるでスポンジケーキにクリームを塗るように、滑っていく木べら。「糊置き」と呼ばれる最初の工程です。

図柄をかたどった型紙に、染料が浸透しない特殊な糊を塗っていく作業で、糊が付着した部分は白い生地のまま仕上がります。1枚塗り終えるとその上に生地を折り重ね同様に塗る、繰り返すこと50~60回。重ねた生地が少しでもずれたら、染料がきれいに浸透せず図柄がつぶれてしまうため、正確な折り返しが要求されます。

「ゼロコンマ数ミリの世界やなあ。温度や湿度、柄の細かさを考えて、重なり合う生地にとって一番いい厚みになるように、糊の粘り気は都度調整してるんや」
と小松さんがつぶやきます。

「触ってみ」と、糊を木べらでかき混ぜてさせてもらうものの、まったく思い通りに動かせません。職人さんの腕の筋肉、握った形に変形してしまっているほどの 木べらの持ち手。相当の力と技をもってして「クリームを塗るよう」な所作に到達されていることがわかります。
美しく染め上げる為の要の工程
出来上がりを想像しながら起こす原版
この糊置きのときの型紙の多くを作っているのは、羽衣綿業 さん。てぬぐいのデザインを、シルクスクリーンのような版 にして染料の浸透部分を残した型にしています。本来は伊勢和紙を使って専門の職人さんが型を作るそうですが、圧倒的な後継者不足で手仕事頼みが限界を迎えているそうです。

実は、いとうさんのイラストを型におこすにあたって、日野谷さんから小鮎や人の目、漢字など「点」のような部分のサイズアップの指示が来ていました。何度か修正のやりとりを経て、ようやくGOサインとなったのです。 生地を幾枚にも折り重ねていくなかで、点状の大きさに色を入れるがいかにむつかしいか。
「電話で説明するよりも実際の現場を見てくれたらいっぺんにわかるやろ」
と日野谷さんが笑います。
いよいよ注染へ・・・!
目の前で繰り広げられる職人の技!

糊置きした生地は、すぐに染色に。あらかじめ色味を調合した染料を“ドビン”と呼ばれるジョーロのような専用容器を使って、生地に注ぎ込む工程です。
シューシューとひっきりなしに聞こえる音は、職人さんが足で操るコンプレッサの機械。注ぎ込んだ染料をコンプレッサに吸い込ませて、一気に浸透させていきます。生地をひっくり返し裏側も同様に。


「一色の場合でも、染料を何度にもに分けてかけてるやろ。 一度にかけてもたらいいようなもんやんけどな、ここの工場は絶対にそれをせんのやわ」
羽衣さんそう話す横で、

「手ぬぐいの場合は色がにじんでしまったとしてもそれが味わいやて説明したらそれで済んでまう話でもあるんよ。けど、意識してぼかすのとにじむのは違う。どんな柄でも手を抜いたらあかんて伝えてます。手間はかけんよりもかけた方がええもんができるやろ」
と小松さんは作業を見守ります。
丁寧に真心も注ぐ、職人たちの手仕事

このあと生地は水洗いの「川」、天日干しの「だて」という工程へ。最初に見た、生地がひるがえるあの光景に、いとうさんが描いた湖北のキャラクターたちがが加わりました。
注染には、工程ごとに職人さんがいて、それぞれに独特の
呼び名がついています。糊置きは「板場」、染色は染料が
入っていた壺にちなんで「つぼんど、つぼんだ」、水洗いは「川」、そして干すのは「だて」。


「昔は、水洗いは石津川でしとったからその名残やわ。 鮮やかな色の生地がな、川でゆらいでてきれいやったで。染め物には大量の水がいるから、有名な産地はどこも川が近くにあるもんや」

工場の外の塀から覗き込むと、どんどんの前を流れる米川よりずっと大きくて穏やかな石津川が広がっていました。向こう岸にはぎっしりの住宅地とビル。
「この道何年? そんなん子どもの頃から手伝ってるからなあ」
と話す小松さんも、日野谷さんも、このまちの伝統を川にも見て来た人なのでした。

「これから手ぬぐいを買うたり、使たりする機会があったときに、これは注染やろかって生地を見てくれるようになったらうれしいなあ」
~PHOTO GARELLY~















・ライター/矢島絢子
・カメラマン/矢野祥太(SOF.)
・編集/ミカミユキ(どんどんスタッフ)
